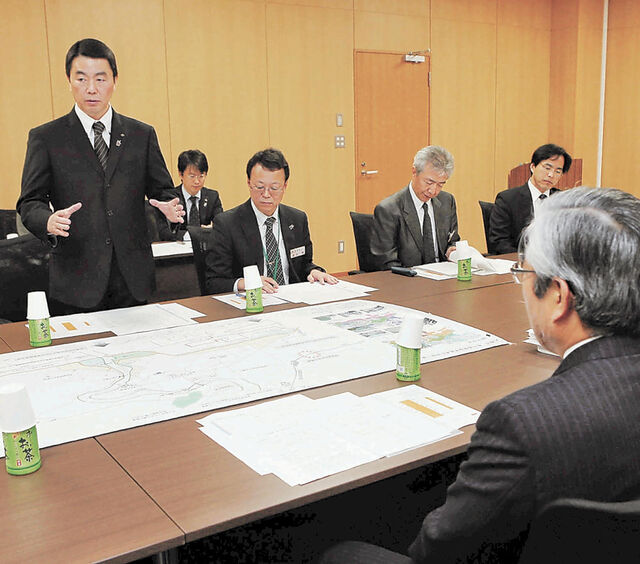
復興の青写真を作る段階から素っ気なかった。
東日本大震災から間もない2011年7月、宮城県の震災復興計画策定に向けた会合の3回目。県が示した案に対し、委員を務めた一般社団法人減災・復興支援機構の理事長、木村拓郎さん(72)は怒りを込めて言葉を発した。
「県民の関心が非常に高いのに、目次に『住宅』という言葉が一つもないのは大問題。中の記述は申し訳ないが3行しかない」
雲仙・普賢岳の火砕流災害や新潟県中越地震など、自治体の復興計画策定に長年関わってきた。「そこに住めないとなって人口が流出したら、復興は失敗だ」。住まいは地域を維持する先行投資と考えていた。
復興基金の使途、生活支援は1割未満
「富県共創」を県政運営の理念に掲げ、産業経済の成長を重視する村井嘉浩知事。復興政策でも姿勢は重なり、県議会で「被災者に寄り添う姿勢がない」などと批判を浴びた。
それを物語る一つの数字が取り崩し型の復興基金の使い道だ。
宮城県によると、11~20年度に活用した県事業分の累計額は518億円。産業振興・地域振興対策が212億円(41・0%)と最も手厚いが、逆に生活支援は46億円(8・8%)、住宅対策は31億円(5・9%)と1割に満たない。
県財政課は「被災地全体の浸水面積の6割を宮城が占める。企業集積地が大規模なダメージを受け、なりわい再生が急務だった」と配分理由を説明する。
住宅対策では、再建のための市町向け交付金や二重ローン対策の利子補助があるが、県独自に国の再建制度を補うメニューはない。
一方、岩手県は国の被災者生活再建支援金に、市町村と共同で最大100万円を上乗せ。支援制度から漏れた被災者にも改修費の一部を補助するなど、住まいに力点を置いた。
「県が主導し手だてを早く用意しなければ、高齢者が再建を諦めたり、人口流出したりする懸念があった」と県復興推進課の担当者は当時の危機感を明かす。
岩手県が11~20年度に充てた県事業の累計は280億円。住宅対策は178億円で全体の63・5%に上る。生活支援は47億円(16・6%)。今も継続している医療費窓口負担の免除にも振り向けた。

内閣府によると、25都府県が被災者生活再建支援制度を補完する恒久制度を設けたが、村井知事は主に財源を理由に難色を示す。
そもそも個人資産への税金投入に否定的で、「税金で全て賄うのではなく、国民全体で賄う共済制度がいいのではないか」(県議会答弁)との発想が根底にある。最近は水災・地震保険の新規加入者に全国で初めて補助を出すなど「自助」にてこ入れする。
全国で災害が起きるたび人口流出や過疎に直面し、高齢者が取り残される。阪神大震災前年の1994年には全国の高齢化率が「高齢社会」の目安とされる14%を突破。2020年には倍の28・8%になった。
木村さんは宮城県の復興に疑問を投げ掛ける。
「右肩上がりの経済ではない時代に、お年寄りは住まいを再建する余裕などない。高齢化がどっぷり進んだ地域の復興はどうあるべきか。住宅再建が地域活性化につながるような、幅広い視点での公助が必要だ」
(報道部・吉田尚史)
[東日本大震災の取り崩し型復興基金]国は2011年、被災9県に原資として総額1960億円を特別交付税で措置。東北では岩手、宮城、福島が半額を市町村に配分した。寄付金を加えた積立総額(市町村分を除く)は岩手県が300億円、宮城県は632億円。国は13年、津波被災地の住宅対策向けに宮城など6県市町村に計1047億円を追加措置した。
関連リンク
関連タグ
からの記事と詳細 ( <耕論・宮城知事選/被災者支援の実相>(2)手薄な住宅再建策、高齢者置き去り - 河北新報オンライン )
https://ift.tt/3liDzHd

No comments:
Post a Comment